気候不安症って知ってる?世界中で起こるたくさんの気象災害に気持ちが落ち込んでいるあなたへ。
世界各地で豪雨被害や大規模な山火事、熱波、そして干ばつなどが続き、気候変動に問題意識を向けているみなさんにとっては気の滅入るニュースが多い日々ですよね。
最近、海外のメディアではEco Anxiety や Climate Anxiety という言葉をよく目にするようになりました。日本語では「気候不安症」「エコ不安症」などと翻訳されます。みなさんはこの言葉を聞いたことはありますか?
こんな時だからこそ、メンタルヘルスについて理解を深めましょう。
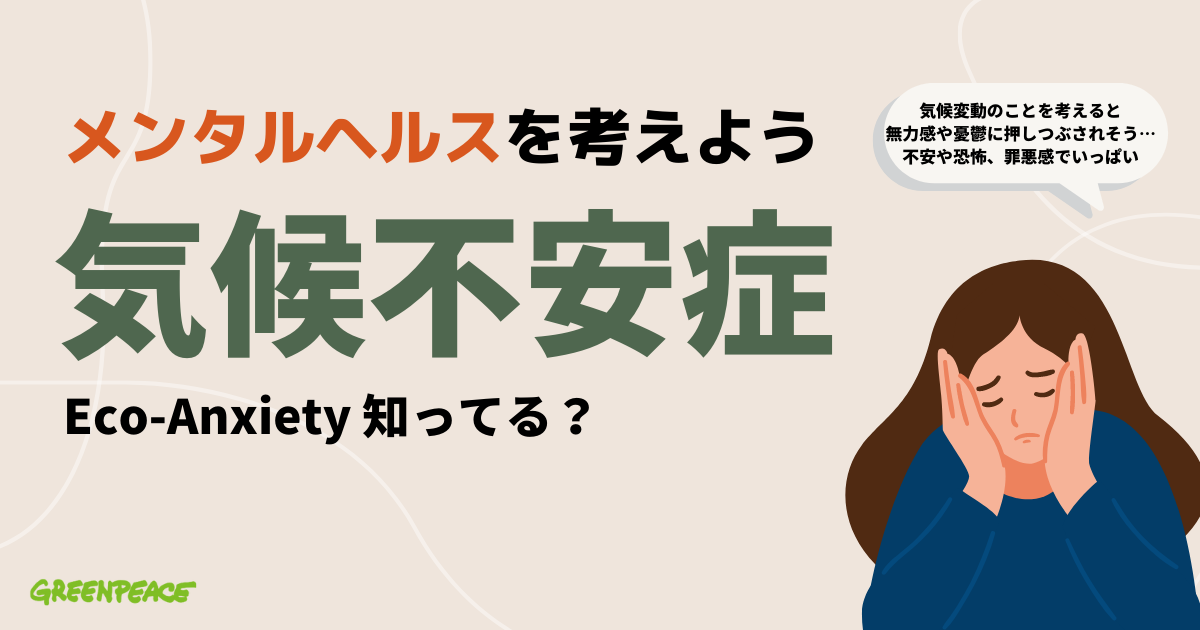
気候不安症とは?
気候不安症は、地球環境の危機的状況に対する慢性的な強い恐怖心のことで、不安感や喪失感、無力感、悲嘆、怒り、絶望感、罪悪感などを強く感じる状態です。
アメリカでは、国民の67%が気候変動が将来に与える影響に強い不安を抱いていると言います。最近では、気候不安症と考えられる子どもの割合も増えてきています。
気象災害のニュースが続いたり、実際に近くで災害が起こったりすると、気候変動が自分や大切な人の命の安全に大きく関わると感じ、危機感が募ると思います。その危機感を原動力に動ける時は良いですが、無力感や無気力感が続き、何もできない場合は気候不安症を疑ってみましょう。

| 気候不安症を知った方の声 「まさしく!これでした? 私だけじゃなかった?✨ 名前がついていたと知るだけで少し安心しました。」 「環境問題のことを勉強して新しいことを知ったり、気候危機に関する日々のニュースを見たりするたびに本当に苦しくて、同じ思いの人がいると知れるだけで少し救いです…」 「災害や環境問題、動物の絶滅危機などの情報を不安に感じているのは自分だけだと思っていました!安心しました!」 |
心が折れて、不安や恐怖で溢れたら
メディアや研究論文を見ると、絶望的なタイトルが書かれていることが多いですよね。
「サンゴの絶滅」「将来の水や食糧不足」「グリーンランドの氷の融解」「〇〇年には△億人が住む場所が居住不可能に」など将来を悲観してしまうものが多いです。
こういった危機感を高める事実はとても大切ですし、危機意識は社会変革の前提条件ということはソーシャルサイエンスでも分かっています。
ですが、もし「心が疲れている」「自分には十分は危機意識がある」と思ったら、まずは絶望的なタイトルではじまる記事は少し読むのをおやすみしてみましょう。

解決策だけに目を向ける期間も大切
日々、問題に目を向けるのは大切なことですが、もし自分の中に既に十分な危機意識があると感じていたら、過剰に不安を増幅させてもバーンアウト(燃え付き症候群)してしまうだけです。
毎日の中で実践できる解決策に目を向け「どんな絶望的な未来が待っているか」ではなく「どんな世界を作りたいか」に軸を置いてみましょう。
例えば、無農薬・無肥料の野菜、プラントベース(植物性)の食事、環境に配慮した日用品の選択、脱使い捨てなど、毎日の生活の中で地球環境と調和して生きていくために選択できることがたくさんあります。
毎日できる解決策を全力で楽しんでやってみる。そんな中で、まずは自分の心を癒すことに集中してみる。こういった時間もとても大切です。

危機感を伝えたい焦りとうまく向き合う
現状を知ると、危機感や何かやらなくてはという焦燥感でいっぱいになると思います。
元気な時は、ぜひそのエネルギーをご自身ができることに使っていただきたいと思います。
心がつらくて気候不安症かも?と感じた時は、環境をこれ以上壊さない消費を選択して、企業や社会に需要を示していくだけでも立派な環境活動だとご自分に言ってあげましょう。
毎日、学業やお仕事や子育てでたくさんのストレスがあるのに、気候変動という果てしなく大きな問題にまで取り組むのは、疲れて当然なんです。
頑張れない自分を否定せず、今日を環境に優しく生きるだけでも、地球市民として素晴らしいことだと思います。
グリーンピースも、科学に基づいた環境問題を伝えることに加えて、行動を続ける希望になるような解決策をお伝えしていけるよう頑張ります。
みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

あなたにできること
自分たちにできることから行動に移すことこそが、未来への希望になります。
- 肉を食べる量を減らして、野菜中心の食生活を心がける
- フードロスを減らす
- 生態系への負担が低いオーガニックの食品を優先する
- 自宅や職場の電気を自然エネルギーに変える
- 資源とエネルギーを無駄使いするプラスチックや紙の使い捨てを減らす
- ファストファッションより、長く大切にできる服を選ぶ
- 選挙では気候変動対策を優先する議員に投票する
- CO2削減など温暖化対策に積極的な企業の製品やサービス、地球環境や人、社会、地域に配慮した「エシカル」な商品を選ぶ
- 移動手段として、CO2の排出量が少ない公共の交通機関を利用するようにする
など、今日から始めて、続けられるアクションの選択肢はたくさんあります。
誰もが安全に、健康に生きられる未来へ、今日行動を始めましょう。