[スタッフVoice] 環境をまもりたい。子どもの頃から温めていた夢は、専門知識がなくても実現できた
[スタッフVoice vol.14]
グリーンピース・ジャパンで働くメンバーのご紹介:コムズマネージャー、N・Hさんのインタビューをお届けします。
専門知識がないから環境保護を仕事にするなんて無理だろう、そう考える人は少なくないかもしれません。けれども、入職時から環境問題に関する専門知識を持っているスタッフのほうが少数です。業務の多くは、スタッフ各自のキャリアや知識こそを必要としています。
グリーンピースの活動を広く伝える広報もそのひとつ。意外にもコミュニケーション能力が重要という業務内容について、そして専門知識がなくても環境をまもる仕事に就けたという体験を聞きました。

ナウシカに心揺さぶられた少女が、グリーンピースの広報となるまで
広報としてグリーンピースで働いて3年のN・Hさんは、子どもの頃から環境問題に強い関心を持っていました。ポーランドにルーツを持つ彼女ですが、生まれ育ったのは日本の自然豊かな地域。自然に囲まれて育ったことと、環境問題を題材にしたジブリ映画の『風の谷のナウシカ』に何より強い影響を受けました。何回も繰り返し観るほど、のめり込んだといいます。
「動物が好きだったので、将来は獣医になりたいと思ったこともあったんですが、数学が大の苦手で…。そういうこともあって、中高生の頃に環境問題に関わる仕事には就けないだろうなとなんとなく思っていました。大学では、語学が得意だったので英語とポーランド語を学んで、ポーランドに留学もしました」
語学以外に、N・Hさんが夢中になったのは、音楽です。音楽に関わる仕事に就きたいと就職活動をし、音楽や映像の配信サービスを行っている会社に就職。ざまざまな配信コンテンツについて文章を書く業務を担当し、そこで磨かれたライティング能力が、のちに広報の仕事に活きてきます。
8年間勤めた会社を退職した後はフリーランスとなり、語学力を活かして翻訳や通訳を主に行う傍ら、アーティストのインタビュー記事や音楽フェスのレポートを書くなど音楽ライターや観光ガイドなども経験し、充実した毎日を送っていました。
けれどもその後、新型コロナウイルスの感染拡大で、生活環境が大きく変わったことが、N・Hさんの人生に大きな変化をもたらすことになります。
「ひとりで家にいる時間がたくさんあったので、いろいろ将来のことを考えたり、環境問題についてのドキュメンタリー番組をたくさん観たり、そういうことをしていたんです。
30代という年齢もあって、転職するならいまじゃないかなって考えたときに、自分がずっと大事に思っていることは環境だったなって思い出したんですよね」
それから、環境問題について調べたり、環境保護活動をしているNGOをフォローしたりしているうちに、グリーンピースの求人にたどり着きます。「広報であれば、自分の持っている力が活かせるのでは」と考え、応募しました。その結果、専門知識がないと無理だと考えていた環境保護を仕事にすることに。
ずっと人生の選択肢に入れてこなかったことが、何十年という歳月を経て現実のものになったのです。

入職後、最初に担当したのはプラスチック問題でした。専門知識はありませんでしたが、入職してから知識を身に着けていくことで、業務に支障になることはなかったと振り返ります。そして、それまでに環境保護とはまったく無縁の仕事で身につけて来たライティング能力が、プレスリリースなど文章をまとめる業務にはおおいに役立ちました。
ただN・Hさんが、広報の仕事にとってライティング能力以上に重要だと考えるのは、コミュニケーション能力です。
「もともと外交的な性格なので、記者の方に話しかけたりするのは躊躇なくできるんですよね。そういうコミュニケーション能力は、広報にすごく大切だと思います。記者の方と日頃から連絡をとっていたり、電話をしたり、記者会見で話したり、そういうコミュニケーションの積み重ねが、カバレッジ(新聞やテレビなどメディアによる報道)につながることもあるんです」
広報は、プレスリリースなどの形でグリーンピースの活動を発信し、それらの情報を新聞やテレビなど、さまざまなメディアに取り上げてもらうことでより多くの人に伝えることが重要な役割です。情報を提供するNGOとそれを報道するメディアと立場が異なっていても、担当するのは一人ひとりの人間同士。そこでどのようなコミュニケーションが交わされるかは、当然重要なポイントになってくるのでしょう。
さらに、リアクティブ(何らかの社会における動きに対してグリーンピースの見解等を伝えるもの)を出すときにはスピード感が求められ、記者会見を実施するときはていねいな準備をしつつ、当日は臨機応変に対応する必要があります。ときにはキャンペーナーと一緒に関係する省庁や企業に足を運ぶことも。幅広いさまざまな能力が必要とされる一方で、広報としての経験が浅くても入職後に学んでいけるようです。
グリーンピースという組織の窓口として、広報の果たす役割とは
広報が発信する内容の多くは、プログラム部のキャンペーナーが実施したキャンペーンの内容や調査の結果に基づくもの。けれども、「グリーンピースが言いたいことだけを発信していればいいのではない」とN・Hさんは語ります。メディアを通して多くの人に伝えるためには、どうすればメディアが記事やニュースにして伝えたいと思うのか、そこまで考える必要があるのです。
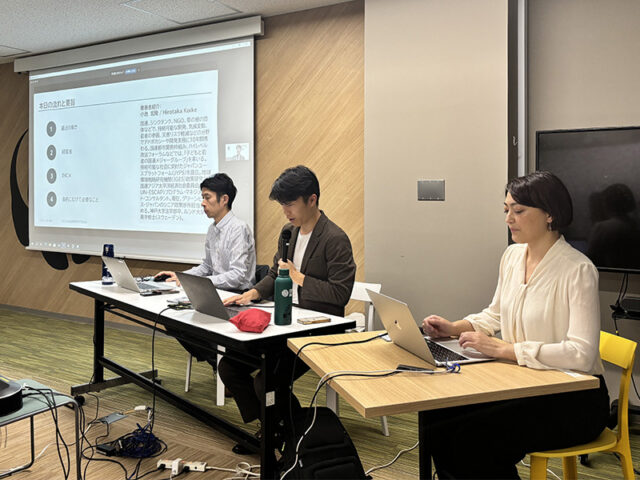
「メディアの人たちは、自分たちの報道をたくさんの人に届けたいわけですよね。だから、社会との接点を見るというか、どういう視点だったら読者に響くのかまで意識しないといけないと考えています。そういう点では、広報担当は、グリーンピースという組織の外側から団体を客観的に見ることができる目線を持たなければいけないと思っていますね」
けれども、キャンペーナーとしては伝えたいことはたくさんあるはずです。そこで、プレスリリースに含まれるキャンペーナーのクオート(コメント)を簡潔にまとめるために、キャンペーナーの思いを尊重しつつ、調整するのは苦労するところでもあるといいます。対外的な窓口である広報だからこそ、組織内で担える役割が存在するのかもしれません。
2024年11月、韓国で国際プラスチック条約に関する国際会議が開催されました。オブザーバーとして会議に参加したグリーンピースの一員として、N・Hさんもグリーンピースの海外オフィスの広報とともに業務を担当した経験は、大きな刺激になったようです。


「渉外担当のスタッフと一緒に、その日の会議の内容を報道関係者向けに説明するブリーフィングを実施しました。海外のメディア向けに英語でもブリーフィングを実施する機会が持てて、挑戦しがいがありましたね。これからは、海外のオフィスが関わるグローバルキャンペーンでも貢献できることには挑戦していきたいなと思います」
子どもの頃からやりたかったことを仕事にし、着実にキャリアを積んでいる毎日。グリーンピースの広報の仕事は、N・Hさんの人生に大きな意味と充実感をもたらしてくれているようです。
「グリーンピースに入る前は、将来の仕事に対して悩むことが多かったんです。いまは、環境問題に関わりたいというひとつの望みが叶えられて、その点ではあまり悩まなくなったかな。それに、環境問題を解決するための活動の一部に自分自身がなっているんだという実感が持てることが嬉しいです」
実は、N・Hさんが高校生だった頃、「将来はグリーンピースで働いていそう」と友達に言われたことがあったそう。予言めいたその言葉が、10年以上の歳月を超えてか現実のものとなっています。
N・Hさんのキャリアや現在の仕事ぶりは、環境をまもりたいという情熱はさまざまなカタチで実を結ぶのだということを伝えてくれるようです。
