富士山頂の気温 100年あたり1.47度上昇、長期的な上昇傾向 気候変動の影響指摘もーー報道発表資料『富士山が告げる気候変動の兆候』
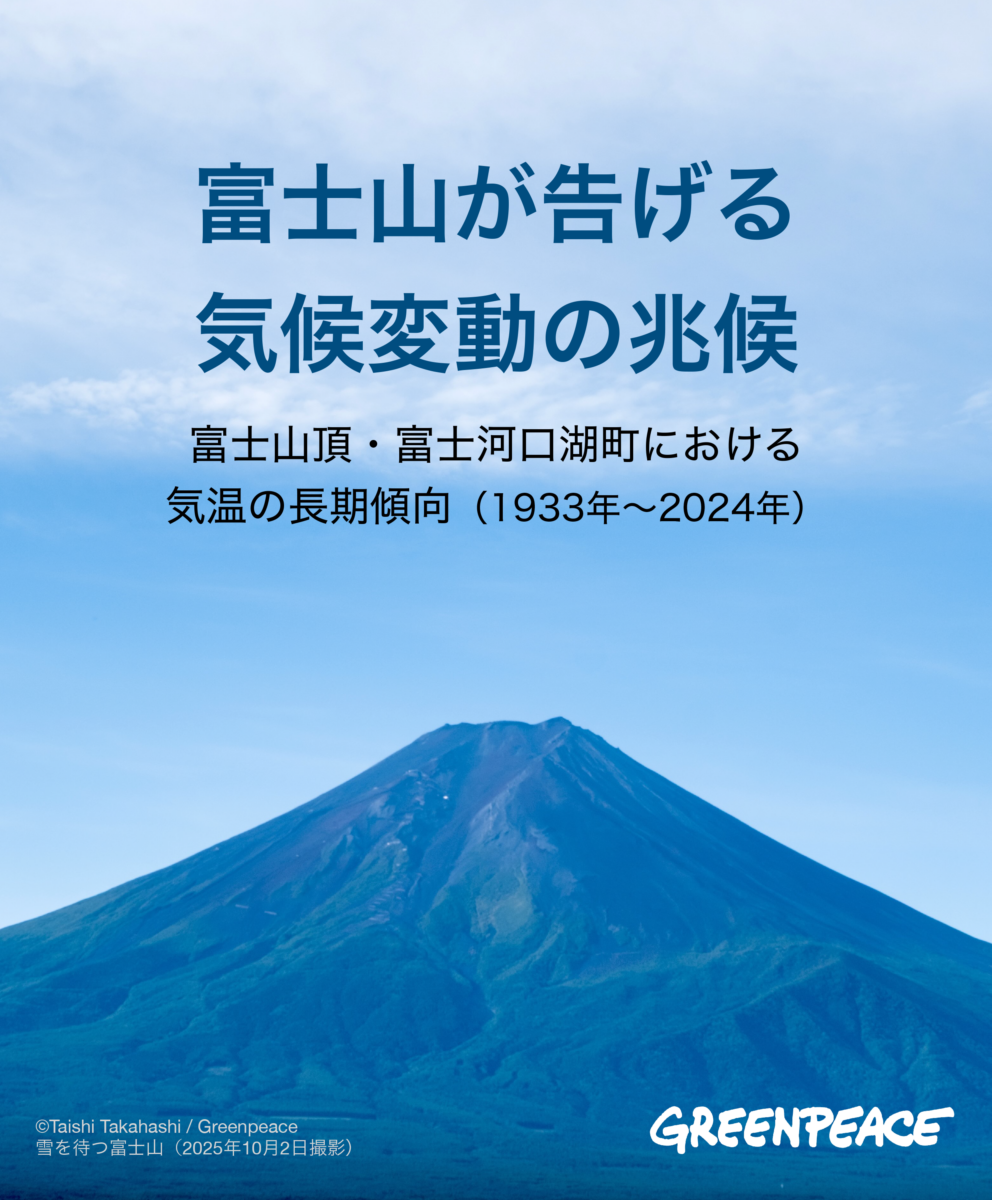
国際環境NGOグリーンピース・ジャパン(東京都港区)は10月2日、富士山の気象データを分析した報道発表資料『富士山が告げる気候変動の兆候ー富士山頂・富士河口湖町における気温の長期傾向(1933年~2024年)』を発表しました。本資料では、1933年から2024年までの92年間の気象庁の観測データをもとに、富士山頂と麓の山梨県富士河口湖町の気温の分析を行いました。年平均気温は富士山頂で100年あたり1.47度、富士河口湖町で同2.64度のペースで上昇しています。専門家からは長期的な平均気温の上昇傾向から、地球温暖化の影響を指摘する声もあり、世界的な気候変動が、富士山の気温の変化に影響を与えている可能性があります。なお、本日10月2日は、甲府地方気象台による富士山の初冠雪の平年値にあたります(注1)。
>>Please see the English version here
<報道発表資料の主なポイント>
- 富士山頂の年平均気温は、長期的に上昇傾向を示しており、全国の年平均地表気温が100年あたり1.35度上昇したのに対し、富士山頂では1.47度の割合で上昇している。
- 富士山頂の年間の氷点下日数は減少傾向にあり、特に観測史上最も高い年間平均気温(-4.2度)を記録した2024年には、氷点下日数が過去最少の250日となった。この減少傾向は、特に6月、9月、10月に顕著にみられる。
- 富士山頂の冬季(12〜2月)平均気温は、100年あたり1.70度上昇しており、全国の冬季平均気温(1.19度)を上回った。特に2月の上昇が顕著な一方、12月は比較的安定している。
- 富士河口湖町では、年間平均気温が100年あたり2.64度上昇しており、2023、2024年は過去最高を1度超更新した。氷点下日数も急速に減少しており、年間平均124日から、100年あたり26.74日のペースで減少した。
- 富士河口湖町の冬季平均気温は、長期的に0度を上回る方向へと変化している。1933年〜1953年の冬季は0度を下回る年が多かったが、1987年以降は、ほぼすべての年で0度を超えている。特に2月の変化が著しく、1935年〜1944年と2015年〜2024年を比較すると、約3.5度の上昇が見られる。
東京大学先端科学技術研究センター シニアリサーチフェロー、中村尚 名誉教授
「温暖化に伴う水蒸気量増加の影響が含まれるため、富士山における降雪量は必ずしも減少するとは限りません。一方、富士山頂の気温時系列については、長期的な気温の上昇傾向が明瞭なこと、最低気温が0度未満の冬日が減少傾向にあることから、ここ40〜50年は地球温暖化の影響が現れているものと思われます」
グリーンピース・ジャパン プロジェクト・マネジャー、高田久代
「日本ではすでに世界平均を上回るペースで気温が上昇していますが、それをも超える富士山頂の気温上昇率を大変憂慮します。カエデやイチョウの紅葉時期は年々遅れる傾向にあり(注2)、結氷の状態から長野県の諏訪湖では室町時代から続く伝統神事『御渡り(御神渡り)』が7年に渡って執り行えない(注3)など、地球温暖化・気候変動の影響は、四季ある日本の姿を静かに変え始めています。自然界の兆候を的確に捉え、私たちが温室効果ガス削減を加速できるかが、次の30年の日本の四季を左右します」
以上
(注1)甲府地方気象台 気候・気象観測統計
(注2)報道発表資料『紅葉時期にみる気候変動の影響について』(2023年9月)
(注3)リリース『諏訪湖の「御渡り」、雪景色に波打つ湖ーー観察期間終了間近も湖面結氷せず』(2025年2月)