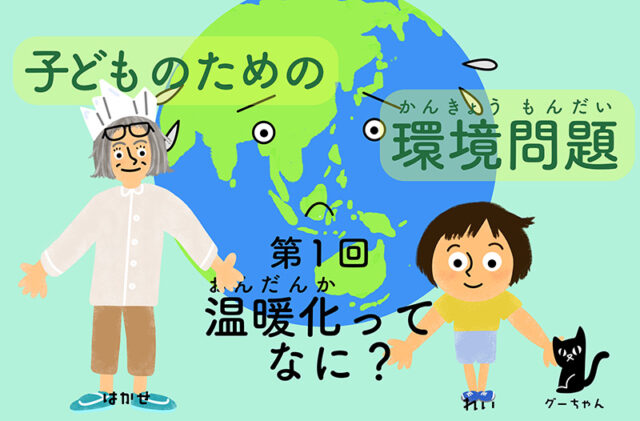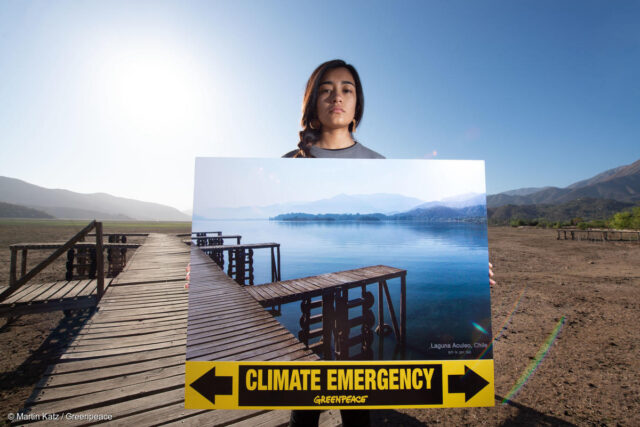記事の投稿-トピック
トピックに関する投稿は、以下の一覧からご覧いただけます。
688件の投稿
-
緊急!新しいネオニコ系農薬、解禁間近。パブコメ・署名で止めよう!
皆さんこんにちは、食と農業担当の関根です。…
-
海がプラスチックでいっぱいになる前に(前編)
こんにちは。海洋生態系担当の小松原和恵です。皆さんは、海とどんなつながりがありますか?美味しい魚の恵み、心とか…
-
食卓のサーモンが、イルカやクジラの海を汚す
皆さん、こんにちは。海洋生態系担当の岡田です。……
-
グリーンピースの目指す「顔」とは
facebookでシェア>ツイートする>事務局長就任から今月で6カ月になります。2月9日、グリーンピース・ジャパンが日頃からお世話になっているNGO、企業、メデイア、政府の関係者をお招きし、東京・表参道で事務局長就任パーティを開きました。幅広い分野から約50名の方々にご出席いただき、親交を深めることができ、改めてこうした絆の大切さを強く感じています。新しい事務局長として、個人的にご挨拶し、グリーンピースのスタッフ、活動をご紹介し、今後の抱負について皆様に共有する貴重な機会となりました。 参加してくださった方の中には、環境や反原発運動に関わる市民団体や活動家、ジャーナリスト、弁護士、議員秘書、環境、開発や人権分野の国際NGOのほか、環境に対する配慮を求め対話を続けている小売業や製造業の方もいらっしゃいました。グリーンピースは環境保護活動を行なっていく上で、様々な立場の個人や組織の方達と協力関係あるいは緊張関係にあります。接点となる関心事項によって意見や立場は分かれても、信頼関係があってこそ、互いに対話を通して認識を共有し最善策を模索することができます。特定の課題についての話し合いという場を離れて、まずお互いを個人的によく知って、団体としての立ち位置や方向性を深く理解するのは、とても有意義なことだと思います。 グリーンピースに求められていること参加者の方々からは、キャンペーン団体として、市民社会の一員として、または交渉相手として、グリーンピースらしさを保ちながら、より開かれた団体であってほしいという期待をいただきました。国際NGOの参加者の方からは、NGOのコミュニティに積極的に関与してほしいとメッセージをいただきました。CSR雑誌の方からは、「グリーンピースはなぜ嫌われるのか」という問題提起があり、グリーンピースのブランドについてコメントをいただきました。メデイアの方からは、グリーンピースの職員2名が多額の税金が投入されてきた調査捕鯨での不正を告発したにもかかわらず、逆に逮捕されてしまった事件の報道の際に感じられた、社会の圧力とご自身の心の葛藤をお話しになり、ジャーナリストとしてご自身の信念を貫かれる強い決意を共有されました。 また、企業からの参加者の方の中では、グリーンピースからの批判が会社の経営を改善していく良い契機になったという声も聞かれました。でも『お手柔らかに』とのご要望も。他を知ることは自分を知ること。それぞれ異なる立場や視点から、グリーンピースの持つ様々な『顔』を鏡のように映し出していただいた思いです。 変化するグリーンピースこれまで、グリーンピースは欧米の団体と見られ、強い信条を持っていてもそれは独善的だ、あるいは一方的な価値観の押し付けだと違和感や反発を覚える方もいらっしゃると思います。きっと、荒々しい海で捕鯨船を追跡する、行動力はあっても一匹狼的な白人男性のイメージを思い浮かべる方もいらっしゃることでしょう。 でも、時代の変遷や社会の変化に伴い、グリーンピースも基軸を保ちつつ柔軟に適応し変化を続けています。グリーンピースは欧米で生まれましたが、今や日本を含む世界55カ国・地域で活動するグローバルな団体です。それに伴い、組織も積極的に多様性を取り入れてきました。当初は白人男性が本部事務局長のポストを占めてきましたが、近年では、外部から抜擢された南アフリカ出身のクミ・ナイドゥ前事務局長に続き、ジェニファー・モーガンとバニー・マクダーミッドという二人の女性が昨年、共同の事務局長に就任しました。共通のグローバルな目標を目指しながら、各国の状況に応じてそれぞれ自主的に行動が起こせる仕組みが作られています。また、各国や地域でも外部から採用された現地出身の事務局長の比率が増えています。 よりオープンな団体にグリーンピースは、今後も、強い信念と情熱をエネルギーに、個人の寄付と支援で成り立つ独立した市民団体として、権力を恐れず、政府や企業に環境保護と社会に責任ある行動を求めていきます。PositiveThinking,ThroughAction(前向きに考え、まずは行動!)」をモットーに、環境破壊の現場からの事実をお伝えしダイナミックなアクションを起こしていきたいと思います。 しかし、より複合的で、社会構造に深く根ざしている今日の環境問題は、グリーンピースだけでは解決できません。グリーンピース中心のキャンペーンから脱却し、志を同じくする他団体とパートナーとして協力し、より広く様々な方からの共感と参加を得られるようなキャンペーンを心がけています。 天然で最も硬い石であるダイヤモンドは、ダイヤモンドによってのみ磨くことができ、激しい圧力や摩擦によってより輝きを増すそうです。人も、周りの人達と真剣に接しぶつかる中で強くなり磨かれていくのでしょう。真っ暗な地中でキラキラ輝く結晶のように、グリーンピースも多くの出会いや様々な交流を通して、これからも、より磨きをかけ成長を続けていきたいと思います。グリーンピースは、政府や企業からお金をもらっていません。独立した立場だからこそできる活動で、私たちの知らないところで進む環境破壊や生態系への影響を明らかにしています。寄付という形でも一緒にグリーンピースを応援していただけませんか?寄付する facebookでシェア>ツイートする>あなたにオススメ!プラスチックから海を守るためのたった5つのシンプルな方法年間800万トンのプラスチックが、世界の海に流れ出ている 「ネオニコを減らし、国産有機を増やす」イオンに声が届いた! 子どもをまもりたい 3.11原発事故被害者の人権をまもる国際署名 放射線管理区域で暮らせますか?
-
放射線管理区域で暮らせますか?
こんにちは。グリーンピース、放射線防護アドバイザーのヤン・ヴァンダ・プッタです。全村避難をした福島県の飯舘村の避難指示解除が3月31日と言われています。東京電力福島第一原発から30キロ以上離れているのに、吹いた風にのって高濃度の放射能が降り注いだ飯舘村。グリーンピースは、もしいま飯舘村に帰って、事故前と同じように生活したら、どのくらい被ばくするリスクがあるのか、飯舘村の住民の方々のご協力のもと、調査しました。住民の方のお宅7軒で、2万3080カ所で放射線を測りました。その結果、もし、これらの方々がいま帰還すれば、生涯(70年間)で少なくとも39ミリシーベルトから183ミリシーベルトの範囲で被ばくする可能性があることが明らかになりました。「政府はこの先どうなるのか教えてくれない」3年間以上、グリーンピースの放射線調査に協力してくださっている飯舘村村民の安齋さん。「お役所は、これから先自分がどうなるのかを教えてもくれずに、帰れ、帰れって言うばかり。グリーンピースは、家もまわりもこまかーく測ってくれて、帰ったらどれだけ被ばくするのか、言ってくれて助かる。帰るか、帰らないか、自分で決めたい」調査結果の発表に先立って、安齋さんをはじめ、調査に協力してくださった住民のみなさんにご報告にうかがうと、安齋さんはそうおっしゃり、報告内容を聞いてくださいました。私は、「帰る、帰らないを決めるのは、住民のみなさん自身です。どちらを決めても、その意思を尊重します」とお伝えした上で、ご報告しました。「放射線管理区域」で暮らせますか?安齋さんのお宅周辺では、平均毎時0.7マイクロシーベルトが計測されました。これをもとにすると、2017年から70年間の生涯被ばく線量は約90ミリシーベルトになると推定されます。**下表より、屋外で8時間過ごす場合。レポート「遠い日常」より。空間線量の推移を、放射線崩壊を考慮に入れて予測し、累積線量を見積もった。これには、高濃度の放射能が飛散した事故直後の被ばくは入っていません。また、被ばくには、体の外から受ける外部被ばくと、呼吸や食べ物から体内に取り込まれる内部被ばくがありますが、内部被ばくは入っていません。それから、放射能は、時間とともに弱まっていくのを計算に入れています。しかし、たとえば、除染していない森から流れてくる放射能による再汚染などは入っていません。 つまり、事故直後の被ばくや、内部被ばく、森から流れてくる放射能の再汚染などによって、さらに生涯被ばく量が上がる可能性も考えられます。チェルノブイリ原発事故の被害を受けたウクライナでは、生涯に70ミリシーベルトを超える放射線を浴びてはいけないとしていますが、安齋さんのお宅では、これをはるかに超えて被ばくしてしまうことになります。また、毎時0.7マイクロシーベルトというのは、本来、「放射線管理区域*」にすべき線量です。なお、毎時0.7マイクロシーベルトという数値は、安齋さんのお宅の様々な地点で測った数値の平均です。実際には、安齋さんにお話を伺いながら、事故前の普段の生活で使っていた場所を、この表のようにゾーンごとに測定しています。ゾーンごとに平均を出し、さらにその加重平均の数値が毎時0.7マイクロシーベルトです。 *放射線の不必要な被ばくを防ぐため、放射線量が一定以上ある場所を明確に区別し人の不必要な立ち入りを防止するために設けられる区域。法令により定められている。毎時では0.6マイクロシーベルト以上。「とても帰れない」また、今回、政府のいう「木造家屋内にいれば、屋外の放射線の6割はカットできる」というのは過大評価の可能性があることも明らかになりました。 家の外と中の線量を比べても、それほどカットできていないことがわかりました。例えば安齋さんのお宅では、家の外の加重平均値は毎時0.7マイクロシーベルトでした。政府のいうように、6割がカットされるなら、年間換算では2.5ミリシーベルトになるはずです。しかし、安齋さんのお宅の中に設置した個人線量計*は、年間5.1から10.4ミリシーベルトを計測しています。レントゲン1回が約0.05ミリシーベルトとすると、5ミリシーベルトでは100回分になります。 安齋さん宅も、公衆被ばく限度の年間1ミリシーベルトに下がるまでには、50年かかる可能性があります。安齋さんは、「とても帰れない」と話されていました。 *個人線量計(ガラスバッジ)は、 個人が受けた放射線量を積算したものがわかる線量計です生涯にわたって受ける線量を推計するために今回は、4つの手法で放射線調査を行いました。1)敷地内を10ほどのゾーンに分けて、その中を規則的に歩いて、1秒ごとに計測するこのとき、ホットスポットは探さない。1つのゾーンにつき、地上1メートル高さの放射線量を、100から1,000カ所くらい計測する。細かく測った上で平均を出すことで、そこがどれくらいの放射線量なのかわかる。2)1つのゾーンで、2つの土壌を採取して、土壌中の放射能を分析する分析できるのはセシウム。放射能が弱くなるスピードが違うセシウム134とセシウム137の比率を調べる。そのことによって生涯線量を計算するときに使う計算式が実際とあっているかどうか検証する。3)ゾーンの中のホットスポットを探して測る平均値ではわからない、特に放射線量の高い場所がわかる4)個人線量計(ガラスバッジ)の設置と回収長期的にどれくらいの被ばくをするのか予測できる。今回は、2つのお家の中と外に、計4つずつ設置しました。生涯被ばく線量を計算するのに、必要なのは1)と2)。そして、自宅に戻った時にとても気をつけなければいけないのが、敷地内のホットスポット。そして、家の中でどれくらい被ばくするか、がわかる屋内に設置した個人線量計。それぞれが、自宅に戻った時に、どれくらい被ばくするのかを考えるのに、役立ちます。全くおかしい年間20ミリシーベルト基準国による避難指示解除の条件は、この3つです。1)年間20ミリシーベルト以下になることが確実であること2)電気、ガス、水道、交通、通信などのインフラや、医療・介護・郵便などが復旧すること除染が十分に進捗すること3)県、市町村、住民との十分な協議 たしかに、今回の調査では年間20ミリシーベルト以下になることがほぼ確実でした。実は、この20ミリシーベルトというのは、避難指示を出す基準でもあります。しかし、2011年に年間20ミリシーベルトであることと、今、年間20ミリシーベルトであることは全く違います。…
-
飢えで命を落としたクジラ、実はあるものでお腹がいっぱいだった?
こんにちは、海洋生態系担当の岡田です。 まだまだ寒い日が続いていますが、みなさん、如何おすごしでしょうか?…