【イベント報告】第2回国際プラスチックシンポジウムを開催

世界が一丸となってプラスチック汚染を解決するための条約がいま、作られようとしています。2022年に国連で制定が決定した「国際プラスチック条約」です。内容の大枠が決まるはずだった2024年11月の政府間会合(INC-5)では参加国の溝が埋まらず不合意で終わったものの、会合を追加で開催し、条約の策定を変わらず目指していく予定です。
ただ「解決」とひと口に言っても、とても複雑なプラスチック問題(以下、プラ問題)に取り組むには、政府や自治体、企業など各界がそれぞれの課題を理解し協力し合うことが欠かせません。
そこで条約の策定に先立ち、グリーンピース・ジャパンではプラ問題に取り組む各界の現状や課題、条約に求めることなどを共有し合う場として、イクレイ日本とともに「国際プラスチック条約シンポジウム」を2024年10月に開催しました。専門家や若者の意見も交えて、脱プラスチックに今後どう取り組むべきかの議論が繰り広げられました。
ここではシンポジウムでの内容を振り返ります。
脱プラスチックに効果的に取り組む方法
最初の登壇者は、国立環境研究所・資源循環社会システム研究室の田崎智宏(たさき・ともひろ)室長とグリーンピース・ジャパン・シニア政策渉外担当の小池宏隆(こいけ・ひろたか)。脱プラスチック(以下、脱プラ)に効果的に取り組むために挙げられた主なポイントは以下でした。
有効な対策に優先的に取り組んでいく
田崎室長が挙げたのは、有効な対策に優先的に取り組んでいくこと。そのためにはまずプラ問題が複数の環境問題を引き起こしていることを理解するのが大切だといいます。
以下の表ではそれぞれの問題に対して、どの対策が効果的なのかをチェックマークで示しています。
問題解決のための対策 | プラスチックが引き起こす問題群 | |||||
| 海洋プラスチック汚染、マイクロプラスチック汚染 | 石油依存問題 | 生物多様性への危機 | 地球温暖化 | 大量生産・大量消費 | ||
| A | リデュース | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| B | リサイクルの促進 | ✔︎ | ||||
| バイオマス起源素材への代替 | ✔︎ | ✔︎ | ||||
| C | 海洋分解性素材への代替 | ✔︎ | ||||
| 環境クリーンアップ活動 | ✔︎ | |||||
| 収集の促進 | ✔︎ | |||||
プラスチックが引き起こすすべての問題に有効なのは、リデュースであることがわかります。そのほかの対策は、一部の問題への対策にすぎません。よってプラ問題に包括的かつ効果的に取り組むには、A、B、Cの対策の掛け合わせが必要だと田崎さんは解説。
ただ同時に注意すべきなのは、取り組むだけでよしとせず、先を見据えて行うこと。たとえばリサイクルをしても使い手が見つからず資源を無駄にしたり、代替品を取り入れることで森林伐採など別の環境問題を加速させたりすることもあります。このように取り組み方によっては、解決策が新たな問題を生み出す要因となる可能性があることを指摘しました。
なかでも優先的に取り入れていきたいのは、あらゆる問題に効果的なリデュース。それにくわえてリユースも最優先とすることを推奨しました。
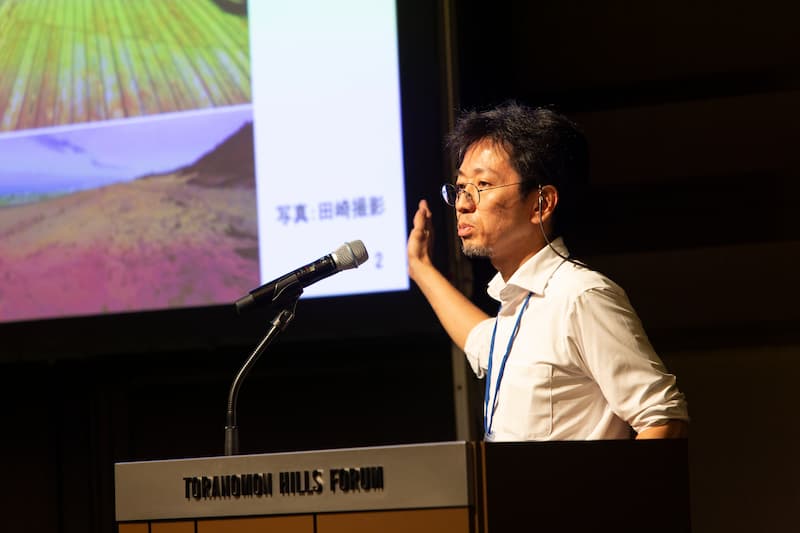
1.5度目標を達成する視点から考える
グリーンピース・ジャパンの小池が挙げたのは、1.5度目標(※)を達成する視点から考えて、動くこと。そもそもプラスチックがこのままのペースで生産され続ければ、1.5度目標は達成できず、気候変動の悪化をくい止めることは難しくなると推測されています。プラスチックは化石燃料由来で、採掘・生産から廃棄までのすべての過程で気候変動を加速させるCO2を排出するためです。
※1.5度目標とは、気候変動対策に取り組むうえでの国際的な目標。世界の平均気温の上昇を産業革命前と比べて、1.5度に抑えることを意味する。2020年11月に開催された第26回気候変動枠組条約締約国会議(COP26)にて、この目標が明示された。1.5度を超えてしまうと、気候変動の影響がより危機的になることが推測されていることから、この目標の達成が世界的急務とされている。
特にプラスチックは「つくる」から「製品に変わる」までの段階で、ライフサイクル全体の二酸化炭素(CO2)排出量の9割を排出します。そのためリサイクルのように「製品ができたあとに対処する方法」では、1.5度目標の達成に貢献できないと主張します。
ならば、どうすべきか。
まずは「必要不可欠なもの」と「必要不可欠ではないもの」を見分けること。たとえば脱炭素に有効な太陽光パネルなどにもプラスチックは使われていますが、使い捨てカップなどより優先度が高く、長く使われ続けます。
限られた資源は必要性の高いもの(※)に使い、見直しを検討できるものはリデュース・リユースへと積極的に置き換えていくこと。さらにはCO2の排出量が低い再生材・代替材が普及するよう、生産規模を拡大し、国際的に公平な価格競争がなされる取り決めを行うこと。小池は、プラスチックから効果的に脱却する方法として上記を挙げ、これらに取り組みやすくなるための条項を含むことを条約に求めました。
※小池は必要性の高いプラスチックとして、医療や、脱炭素を進める取り組みに利用されるものとしました。

政府・企業・若者はそれぞれ国際プラスチック条約に何を求めている?
続いて1回目のラウンドテーブルでは、グリーンピース・ジャパンの小池がファシリテーターを務め、プラスチックの削減に取り組む政府や企業、若者に、条約に求めることを聞きました。
ここでは、以下3名が登壇。
(1) 小林豪さん(こばやし・ごう 環境省 水・大気環境局海洋環境課 交渉官)
(2) エリック・カワバタさん(テラサイクルジャパン/Loop Japan 代表 アジア太平洋統括責任者)
(3) 松倉杏奈さん(まつくら・あんな プラスチック若者会議 メンバー)

政府が条約に求めること
日本は2023年のG7広島サミットで「2040年までにプラスチックによる追加的汚染ゼロ」を掲げました。環境省の小林さんは、それを実現していくうえでも、ライフサイクル全体への取り組みが大切だと言及。また、必要な対策は各国ごとに異なるとし、自国での問題に効果的に取り組めるよう各国が行動計画を提出し、透明性をもつことなどを条約に求めました。

企業が条約に求めること
テラサイクルのカワバタさんは、民間企業と協力し、化粧品のパッケージや洗剤の詰め替えパックなどのリサイクル回収やリユースシステムの運用・構築に取り組むなかで、システム規模を拡大することの難しさを指摘。民間企業の取り組みだけでは経済合理性が見合わないこともあることから、規模拡大を後押しするような取り決めなどが条約に必要だと主張しました。

若者が条約に求めること
プラスチック若者会議の一員として、30歳以下の若者約50名とともに政策提言書を作成してきた松倉杏奈さんは、提言書の内容を発表。そのなかには、プラスチック削減目標の設定を義務付けることをはじめ、生産者から消費者まで責任を分配できる「プラスチック容器包装税の導入」や、若者の参画の場として市民会議を設けることなど、具体的な案が盛り込まれていました。

3者が条約に強く求めたこと
3名ともが強調した懸念点は、先進国が大量のプラスチックを生産し続けていること、そして処理できない分を途上国に押し付けてしまっていること。これらの懸念点を解決するためにも、途上国の人権や健康をまもるようなしくみや、途上国が必要とする廃棄物処理システムの構築支援などを条約に求めました。
企業や自治体での脱プラスチックに向けた取り組み
2回目のラウンドテーブルでは、イクレイ日本の内田東吾さんがファシリテーターを務め、プラ問題の解決に向けた企業や自治体などの具体的な取り組みについて聞きました。登壇したのは、以下の方々です。
- 榎堀都(えのきぼり・みやこ CDP Worldwide-Japan アソシエイトディレクター/ディスクロージャー)
- 荒井和誠 (あらい・かずみ 東京都 環境局資源循環推進部計画課 資源循環計画担当課長)
- 中村健太郎(なかむら・けんたろう クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(以下、CLOMA) 事務局主幹)

情報開示
最初に発表をしたのは、CDP Worldwide-Japan(以下、CDP)の榎堀さん。CDPは、企業や自治体に向けた情報開示システムを運営し、プラ問題をはじめ、さまざまな環境問題に働きかけてきた団体です。CDPによると、情報が開示されていると評価がしやすく、資金調達の可能性も生まれやすいため、その価値はとても大きいとのこと。実際に企業間でも「収益性を確保していくうえで、情報開示は必要」という考えが広まっているそうです。
とはいえ、「どこから手をつけたらいいかわからない」という課題に直面する企業も多いそう。そこでCDPは情報開示に対応できる質問書を作成することで、開示に必要な行動を明確化し、開示の促進を支援しているといいます。
| CDPのプラスチックにおける質問の例 ・販売したポリマーの総重量 ・販売/使用したプラスチックパッケージの総重量とそれに含まれる原料 ・プラスチック廃棄物の総重量と使用済み廃棄物の管理経路など |
質問書をもとにプラスチックの情報を開示したのは、世界で約3,000社、国内で約600社以上(2023年時点)。情報開示をする企業が増えることは、脱プラの促進にもつながります。また、企業における脱プラの重要性を理解している企業ほど、脱プラに関する高い目標に取り組んでいるそうです。
今後条約が採択され、国の政策に落とし込まれたとき、日本独自の基準にならないことが大切だと指摘。グローバルに活躍する日本企業もたくさんいるなかで、国際基準に則って情報開示をしていくことが理想的だと語りました。

サーキュラーエコノミーの実現
東京都環境局の荒井さんは、CO2実質ゼロを目指すうえでも、資源を新たに生み出すのではなく、すでにある資源を循環させていくサーキュラーエコノミーが広がっていくことが大切だと言及。そのためにも2R(リデュース・リユース)や、プラスチックをプラスチックに再生する水平リサイクル(マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル)を推進しており、これらに取り組む企業などには補助事業を設けていることを説明しました。ただ、経済合理性でいうと、使い捨てプラスチックとリデュース・リユースのシステムのあいだには圧倒的な差があり、2Rなどを推し進められる条約になることを期待すると話しました。

バリューチェーンの連携
プラスチックごみの解決に向けた官民連携の会員制プラットフォーム「CLOMA」を運営する中村さんは、1社だけでは資源循環の効果を最大化しづらいことを指摘。そこでCLOMAは製品の生産から廃棄までにかかわる事業者をつないでいく「バリューチェーン連携」を軸とし、企業が協業してリサイクルなどに取り組めるビジネスマッチングを行っていることを説明。リサイクルの動きをもっと広げていくには、大きなブランドのリードも必要だと語りました。

まとめ
プラスチック削減に取り組む政府や企業、若者を交えて開催された「国際プラスチック条約シンポジウム」。各界からはプラ問題の対策としてリデュース・リユースが重要だとする指摘や、リユースの取り組みなどに経済合理性が求められている点などが言及されました。
リユースや脱プラへの取り組みが世界でどこまで広がるかについては、国際プラスチック条約が大きなかぎを握ります。グリーンピースでは強力な条約が実現されるよう、これまでも条約の政府間会合にオブザーバーとして参加し、2040年までにプラスチックの生産量を75%削減する(2019年比)ことなどを各国政府の代表に求めてきました。また、野心的な条約を求めて集めた署名を交渉に参加する政府代表らに直接提出し、力強い条約を後押ししました。署名は、世界自然保護基金(WWF)、国際的な脱プラスチックネットワークBreak Free From Plasticsと合同で提出し、数にして約290万筆(グリーンピースの提出分:約200万筆)にもおよびました。
2024年11月に開催された5回目の政府間会合では各国の溝が埋まらず合意に至らなかったものの、グリーンピースは追加で開催される会合にも引き続き参加し、効果的な条約を最後まで粘り強く求めていきます。
このような国際条約の政府間会合へのオブザーバー参加をはじめ、地球をまもるための活動を続けられているのは、個人のみなさまのご寄付があってこそです。グリーンピースでは政府や企業からの資金援助を一切受けないからこそ、独立した立場で活動することができています。ぜひご寄付を通じて、自然、命、そして未来をまもるための私たちの取り組みをサポートください。